ホーム >>

松下村塾
松下村塾(しょうかそんじゅく)は、江戸時代後期の幕末に長州藩士の吉田松陰が講義した私塾である。
長州萩城下の松本村(現在の山口県萩市)に、松陰の叔父である玉木文之進が1842年(天保13年)に設立し、松陰も学んでいる。
変遷
吉田松陰は1855年(安政2年)に、実家である杉家に蟄居することになり、杉家の母屋を増築して塾を主宰した。
1858年(安政5年)に藩の許可を得るが、松陰が安政の大獄で粛清されたため、わずか3年で廃止された。
藩校明倫館の塾頭を務めた松陰が主宰し、武士や町民など身分の隔てなく塾生を受け入れた。
明倫館は士分と認められた者しか入学できず、町・農民はもちろん、武士に仕えながら卒(卒族)、軽輩と呼ばれた足軽・中間なども入学できなかったのと対照的であった。
短期間しか存続しなかったが、尊王攘夷を掲げて京都で活動した者や、明治維新で新政府に関わる人間を多く輩出した。
塾生名簿は現存しないが、著名な門下生には久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿、入江九一、伊藤博文、山縣有朋、前原一誠、品川弥二郎、山田顕義、野村靖、飯田俊徳、渡辺蒿蔵(天野清三郎)、松浦松洞、増野徳民、有吉熊次郎らがいる。
また木戸孝允も塾生ではないものの明倫館時代の松陰に兵学の教えを受けている。
明治維新の後に復活し、1892年(明治25年)まで存続した。
萩市の松陰神社の境内には、修復された当時の建物がある。
1922年(大正11年)10月12日、国の史跡に指定されている。
管理団体は松陰神社である。
2009年(平成21年)1月5日に「九州・山口の近代化産業遺産群」の一つとして世界遺産暫定リストに追加掲載された。

-
模築
下記のところに松下村塾の模築がある。
松陰神社(東京) - 東京都世田谷区
玉川学園(玉川大学) - 東京都町田市(広瀬淡窓の咸宜園の模築と並んでいる)
山口県立奈古高等学校 - 山口県阿武郡阿武町
竹村記念公園 - 秋田県大館市(当時安田生命相談役であった竹村吉右衛門が奔走して、実現なったもの)
徳山大学 - 山口県周南市
山口放送本社 - 山口県周南市
道の駅萩往還公園 - 山口県萩市(松陰記念館内)
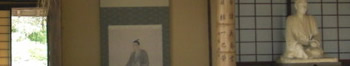 -
玉木文之進
玉木 文之進(たまき ぶんのしん)は、日本の武士・長州藩士・教育者・山鹿流の兵学者。
松下村塾の創立者。
吉田松陰の叔父に当たる。
生涯
文化7年(1810年)9月24日、長州藩士・杉七兵衛の3男として萩で生まれる。
文政3年(1820年)6月、長州藩士で40石取りの玉木正路の養子となって家督を継いだ。
天保13年(1842年)に松下村塾を開いて、幼少期の松蔭を厳しく教育した。
また乃木希典も玉木の教育を受けている。
安政3年(1856年)には吉田代官に任じられ、以後は各地の代官職を歴任して名代官と謳われたという。
安政6年(1859年)に郡奉行に栄進するが、同年の安政の大獄で甥の松陰が捕縛されると、その助命嘆願に奔走した。
しかし松陰は処刑され、その連座により万治元年(1860年)11月に代官職を剥奪されている。
文久2年(1862年)に奉行として復帰し、文久3年(1863年)からは代官として再び藩政に参与した。
藩内では尊王攘夷派として行動し、慶応2年(1866年)の第2次長州征伐では萩の守備に務めた。
明治2年(1869年)には政界から退隠し、再び松下村塾を開いて子弟の教育に務めている。
ところが明治9年(1876年)、前原一誠による萩の乱に養子の玉木正誼や門弟の多くが参加したため、その責任を取る形で11月6日に先祖の墓の前で自害した。
享年67。
山口県萩市に旧宅が保存されている。
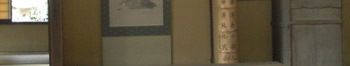 -
吉田松陰
吉田 松陰/吉田 矩方(よしだ しょういん/よしだ のりかた)は、日本の武士(長州藩士)、思想家、教育者、兵学者。
一般的に明治維新の精神的指導者・理論者として名が挙げられることが多い。
贈正四位。
名前
幼時の名字は杉(本姓不明)。
幼名は虎之助。
養子後の名字は吉田、大次郎と改める。
通称吉田寅次郎。
諱は矩方。
字は義卿、号は松陰の他、二十一回猛士。
松陰の号は寛政の三奇人の一人で尊皇家の高山彦九郎のおくり名にちなんでつけられた。
また、「二十一回」については、名字の「杉」の字を「十」「八」「三」に分解し、これらを合計した数字が「二十一」となること、および、「吉田」の「吉」を「十一口」、「田」を「十口」に分解でき、これらを組み合わせると「二十一回」となることによりつけられている。
生涯
文政13年(1830年)8月4日、長州藩士・杉百合之助の次男として生まれる。
天保5年(1834年)に叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となるが、天保6年(1835年)に大助が死去したため、同じく叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で指導を受けた。
しかしアヘン戦争で清が西洋列強に大敗したことを知って山鹿流兵学が時代遅れになったことを痛感すると、西洋兵学を学ぶために嘉永3年(1850年)に九州に遊学する。
また江戸に出て佐久間象山の師事を受けた。
嘉永5年(1852年)、長州藩に無許可の形で宮部鼎蔵らと東北の会津藩などを旅行したため、罪に問われて士籍剥奪・世禄没収の処分を受けた。
 -
嘉永6年(1853年)、マシュー・ペリーが浦賀に来航すると、師の佐久間象山と黒船を視察し、西洋の先進文明に目先を囚われた。
安政元年(1854年)に浦賀に再来航していたペリーの艦隊に対してアメリカ密航を望んだ。
これは開国に求められる豪快そのものであった。
しかし密航を拒絶されて送還されたため、松陰は乗り捨てた小舟から発見されるであろう証拠が幕府にわたる前に奉行所に自首し、伝馬町の牢屋敷に送られた。
この密航事件に連座して師匠の佐久間象山も入牢されている。
幕府の一部ではこのときに佐久間、吉田両名を死罪にしようという動きもあった。
が、老中首座の阿部正弘が反対したため、助命されて長州の野山獄に送られている。
安政2年(1855年)に出獄を許されたが、杉家に幽閉の身分に処された。
安政4年(1857年)に叔父が主宰していた松下村塾の名を引き継ぎ、杉家の敷地に松下村塾を開塾する。
この松下村塾において松陰は長州藩の下級武士である久坂玄瑞や伊藤博文などの面々を教育していった。
なお、松陰の松下村塾は一方的に師匠が弟子に教えるものではなく、松陰が弟子と一緒に意見を交わしたり、文学だけでなく登山や水泳なども行なうという「生きた学問」だったといわれる。
安政5年(1858年)、幕府が無勅許で日米修好通商条約を締結したことを知って激怒し、討幕を表明して老中首座である間部詮勝の暗殺を計画する。
だが、弟子の久坂玄瑞、高杉晋作や桂小五郎(木戸孝允)らは反対して同調しなかったため、計画は頓挫し、松陰は長州藩に自首して老中暗殺を自供し、野山獄に送られた。
やがて大老・井伊直弼による安政の大獄が始まると、江戸の伝馬町牢屋敷に送られる。
幕閣の大半は暗殺計画は実行以前に頓挫したことや松陰が素直に罪を自供していたことから、「遠島」にするのが妥当だと考えていたようである。
しかし井伊直弼はそれほど甘い人物ではなく、素直に罪を自供したことが仇となって井伊の命令により「死罪」となってしまい、安政6年(1859年)10月27日に斬刑に処された。
享年30。
生涯独身であった。
ここで探すのがいいのかもしれない 出会い系ならここで間違いがない。
|

