ホーム >> 吉田松陰

吉田松陰
年譜
1830年9月20日(文政13年8月4日)、長門国萩松本村(現・山口県萩市椿東椎原)に家禄26石の萩藩士・杉百合之助、瀧の次男として生まれる。
1834年(天保5年)、父の弟である吉田大助の仮養子となる。
吉田家は山鹿流兵学師範として毛利氏に仕え家禄は57石余の家柄であった。
1835年(天保6年)、大助の死とともに吉田家を嗣ぐ。
兵学師範としての職責を果たせるよう、同じく父の弟で叔父である玉木文之進から厳しい教育を受ける。
1840年(天保11年)、藩主毛利敬親の御前で「武教全書」戦法篇を講義し、藩校明倫館の兵学教授として出仕する。
1842年(天保13年)、叔父の玉木文之進が私塾を開き松下村塾と名付ける。
1845年(弘化2年)、山田亦介(村田清風の甥)から長沼流兵学を学び、翌年免許を受ける。
九州の平戸へ遊学した後に藩主の参勤交代に従い江戸へ出て、佐久間象山らに学ぶ。
佐久間からは「天下、国の政治を行う者は、吉田であるが、わが子を託して教育してもらう者は小林(小林虎三郎)のみである」と、二人の名前に共通していた「トラ」を引用し「象門の二虎」と褒められている。
1851年(嘉永4年)、東北地方へ遊学する際、通行手形の発行が遅れたため、肥後藩の友人である宮部鼎蔵らとの約束を守る為に通行手形無しで他藩に赴くという脱藩行為を行う。
この東北遊学では、水戸で会沢正志斎、会津で日新館の見学を始め、東北の鉱山の様子等を見学。
秋田藩では相馬大作事件の真相を地区住民に尋ね、津軽藩では津軽海峡を通行するという外国船を見学しようとした。
1852年(嘉永5年)、脱藩の罪で士籍家禄を奪われ杉家の育(はごくみ)となる。
1853年(嘉永6年)、米国のペリー艦隊の来航を見ており、外国留学の意志を固め、同じ長州藩出身の金子重輔と長崎に寄港していたプチャーチンのロシア軍艦に乗り込もうとするが、ヨーロッパで勃発したクリミア戦争にイギリスが参戦した事から同艦が予定を繰り上げて出航した為に失敗。
1854年(安政元年)、ペリーが日米和親条約締結の為に再航した際には金子と二人で停泊中のポーハタン号へ赴き、乗船して密航を訴えるが拒否された。
事が敗れた後、松陰はそのことを直ちに幕府に自首し、長州藩へ檻送され野山獄に幽囚される。
獄中で密航の動機とその思想的背景を『幽囚録』に著す。
1855年(安政2年)、生家で預かりの身となるが、家族の薦めにより講義を行う。
その後、叔父の玉木文之進が開いていた私塾松下村塾を引き受けて主宰者となり、木戸孝允、高杉晋作を初め久坂玄瑞、伊藤博文、山縣有朋、吉田稔麿、前原一誠等維新の指導者となる人材を教える。
1858年(安政5年)、幕府が勅許なく日米修好通商条約を結ぶと松陰は激しくこれを非難、老中の間部詮勝の暗殺を企てた。
長州藩は警戒して再び松陰を投獄した。
1859年(安政6年)、幕府は安政の大獄により長州藩に松陰の江戸送致を命令する。
松陰は老中暗殺計画を自供して自らの思想を語り、同年、江戸伝馬町の獄において斬首刑に処される、享年30(満29歳没)。
獄中にて遺書として門弟達に向けて『留魂録』を書き残す。
その冒頭に記された辞世は“身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂”。
また、家族宛には『永訣書』を残しており、こちらに記された“親思う心にまさる親心けふのおとずれ何ときくらん”も辞世として知られている。

-
思想
一君万民論
「天下は一人の天下」と主張して、藩校明倫館の元学頭・山県太華と論争を行っている。
「一人の天下」という事は、国家は天皇が支配するものという意味であり、天皇の下に万民は平等になる。
一種の擬似平等主義であり、幕府(ひいては藩)の権威を否定する過激な思想であった。
なお、「一君万民」の語を松陰が用いたことはない。
飛耳長目
塾生に何時も、情報を収集し将来の判断材料にせよと説いた、これが松陰の「飛耳長目(ひじちょうもく)」である。
自身東北から九州まで脚を伸ばし各地の動静を探った。
萩の野山獄に監禁後は弟子たちに触覚の役割をさせていた。
長州藩に対しても主要藩へ情報探索者を送り込むことを進言し、また江戸や長崎に遊学中の者に「報知賞」を特別に支給せよと主張した。
松陰の時代に対する優れた予見は、「飛耳長目」に負う所が大きい。
草莽崛起
「草莽」は『孟子』においては草木の間に潜む隠者を指し、転じて一般大衆を指す。
「崛起」は一斉に立ち上がることを指す。
“在野の人よ、立ち上がれ”の意。
安政の大獄で収監される直前(1859年4月7日)、友人北山安世に宛てて書いた書状の中で「今の幕府も諸侯も最早酔人なれば扶持の術なし。
草莽崛起の人を望む外頼なし。
されど本藩の恩と天朝の徳とは如何にして忘るゝに方なし。
草莽崛起の力を以て、近くは本藩を維持し、遠くは天朝の中興を補佐し奉れば、匹夫の諒に負くが如くなれど、神州の大功ある人と云ふべし」と記して、初めて用いた。
この言葉は日本文化チャンネル桜、西村修平、瀬戸弘幸などがスローガンとして用いている。
対外思想
『幽囚録』で「今急武備を修め、艦略具はり?略足らば、則ち宜しく蝦夷を開拓して諸侯を封建し、間に乗じて加摸察加(カムチャッカ)・?都加(オホーツク)を奪ひ、琉球に諭し、朝覲会同すること内諸侯と比しからめ朝鮮を責めて質を納れ貢を奉じ、古の盛時の如くにし、北は満州の地を割き、南は台湾、呂宋(ルソン)諸島を収め、進取の勢を漸示すべし」と記し、北海道の開拓、沖縄(当時は独立した国家であった)の日本領化、朝鮮の日本への属国化、満州・台湾・フィリピンの領有を主張した。
松下村塾出身者の多くが明治維新後に政府の中心で活躍した為、松陰の思想は日本の対外政策に大きな影響を与えることとなった。
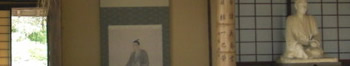 -
ゆかりの地
吉田松陰の故郷である山口県萩市には誕生地、投獄された野山獄、教鞭をとった松下村塾、遺髪を埋葬した松陰墓地、祀った松陰神社等がある。
墓所・霊廟
刑死後、隣接した小塚原回向院(東京都荒川区)の墓地に葬られたが、1863年(文久3年)に高杉晋作ら攘夷派の志士達により現在の東京都世田谷区若林に改葬された。
現在も回向院墓地に墓石は残る。
世田谷区の墓所には1882年(明治15年)に松陰神社が創建された。
また、生地の山口県萩市では死後100日目に遺髪を埋めた墓所(遺髪塚)が建てられた(市指定史跡)他、1890年(明治23年)に建てられた松陰神社(県社)がある。
靖国神社にも維新殉難者として合祀されている。
一族
父・杉百合之助
母・滝
兄・梅太郎(民治)
妹・芳子(千代)、寿(小田村伊之助(楫取素彦)に嫁す)、美和子(初め文,久坂玄瑞に嫁す 後に楫取素彦後妻)
弟・敏三郎
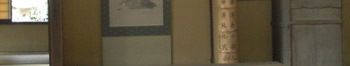 -
久坂玄瑞
久坂 玄瑞(くさか げんずい、天保11年(1840年) - 元治元年7月19日(1864年8月20日))は、日本の武士・長州藩士。
幼名は秀三郎、名は通武、通称は誠、義助。
妻は吉田松陰の妹、文。
長州藩における尊皇攘夷派の中心人物。
贈正四位。
経歴
長門国萩平安古(現・山口県萩市)に萩藩医・久坂良迪、富子の二男として生まれる。
藩校明倫館に入って医学および洋書を学んだのち、安政3年(1856年)、17歳で九州に遊学。
宮部鼎蔵を訪ねた際、吉田松陰の名を耳にする。
帰藩後、松下村塾に学び、高杉晋作、吉田稔麿と共に村塾の三秀といわれた。
松陰は久坂を長州第一の俊才であると認め、高杉晋作と争わせて才能を開花させるようつとめた。
松陰は、久坂を自分の妹文と結婚させている。
安政5年(1858年)、京都・江戸に遊学し、安政の大獄によって松陰が刑死した後、尊攘運動の先頭に立つようになる。
長井雅楽の「航海遠略策」によって藩論が公武合体論に傾くと、文久2年(1862年)同志と共に上京し、長井の弾劾書を藩に提出。
藩論の転換に尽力した。
同年10月、幕府へ攘夷を督促するための勅使三条実美、姉小路公知らと共に江戸に入ると、高杉らと御楯組を結成、12月には品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ちを実行した。
その後、水戸、信州を経て京都に入り、文久3年(1863年)1月27日に京都翠紅館にて各藩士と会合。
4月からは京都藩邸御用掛として攘夷祈願の行幸を画策した。
幕府が攘夷期限として5月10日を上奏するのと前後して帰藩し、下関にて光明寺党を結成。
首領に中山忠光を迎えて外国艦船砲撃事件に加わった。
この頃、義助と改名する。
また再度入京し、尊攘激派と大和行幸の計画などを画策した。
同年の八月十八日の政変によって長州勢が朝廷より一掃された後も、しばらくの間京都詰の政務座役として在京し、失地回復を図った。
しかし、翌元治元年(1864年)6月、池田屋事件の悲報が国許に伝わると藩内で京都進発の論議が沸騰したため、来島又兵衛や真木和泉らと諸隊を率いて東上。
真木和泉らと共に堺町御門で戦ったが(禁門の変または蛤御門の変)、負傷して寺島忠三郎と共に鷹司邸内で自刃した。
享年25(寺島と刺し違えたとも言われる)。
明治7年(1874年)発行の義烈回天百首には、彼の歌が収録されている。
時鳥 血爾奈く声盤有明能 月与り他爾知る人ぞ那起(ほととぎす ちになくこえは ありあけの つきよりほかに しるひとぞなき)
 -
有吉熊次郎
有吉 熊次郎(ありよし くまじろう、天保13年(1842年) - 元治元年7月19日(1864年8月20日))は、日本の武士・長州藩士、尊皇攘夷派の志士。
熊次郎は通称で、諱は良明(もしくは良朋)、字は子徳、本姓は藤原を称し、墓碑の刻字には藤原良明とある。
贈正五位。
作家有吉佐和子の曾祖父にあたる。
天保13年(1842年)、長州藩士有吉忠助の次男(近習有吉傳十郎の弟)として生まれる。
藩校の明倫館に学んだのち、安政4年(1857年)、16歳の時に土屋蕭海の紹介により吉田松陰の松下村塾に入塾する。
松陰は、「才」の岡部富太郎(子揖)、「実直」の有吉(子徳)、「沈毅」の寺島忠三郎(子大)と評して、この3名を一つのグループとして力にしようと考えている。
安政5年(1858年)、松陰の老中間部詮勝暗殺計画に血盟をしたことから、外叔の白根多助により家に幽閉される。
松陰が野山獄に再投獄された際は、その罪状を問うために周布政之助ら重役宅に押しかけた塾生8名の中の一人である。
文久元年(1861年)、高杉晋作に随い御番手として江戸へ遊学、桜田の藩邸内にある有備館に入る。
文久2年(1862年)、高杉ら同志と武州金澤(金沢八景)で外国公使を刺殺しようとしたが、計画が事前に藩主世子の毛利定広に伝わったため実行に到らず、謹慎を命ぜられる。
謹慎中の同志は御楯組結成の血盟書を作る。
この時に血判署名した同志は有吉を含む、高杉、久坂玄瑞、大和弥八郎、長嶺内蔵太、志道聞多(井上馨)、松島剛蔵、寺島、赤禰幹之丞(赤根武人)、山尾庸三、品川弥二郎の11名である。
同年、品川御殿山の英国公使館焼き討ちに参加する。
文久3年(1863年)、藩命により航海術を学び、その後京都学習院への出仕を命じられ、京洛での尊攘運動に邁進する。
同年、八月十八日の政変により帰国後、久坂、堀真五郎らと山口にて八幡隊を結成する。
元治元年(1864年)の池田屋事件では、吉田稔麿ら同志と会合中に新選組に襲撃されるが、乱闘から長州藩邸に逃げ込み、事件の生き証人としてその悲報を国許に伝える。
その際、事件により厳重警戒中の京都を飛脚に変装して出立している。
同年、急進派の藩士らと上京、禁門の変(蛤御門の変)において重傷を負い、久坂、寺島らとともに鷹司邸内で自刃する。
享年23。
墓所は京都市の霊山護国神社、山口市の朝日山招魂社(八幡隊招魂場)。
人気があるのは何故か? 熟女はやっぱりいいものです。
|

